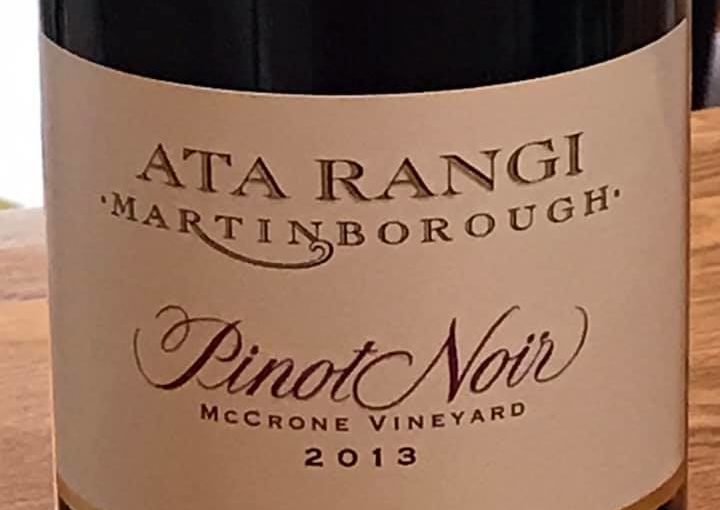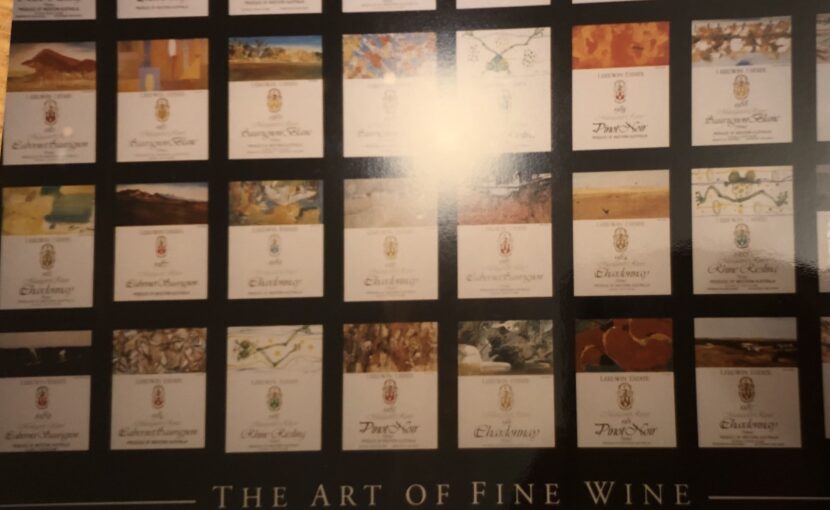エスカは複数の病害が合併して起こる「複合型の樹幹病」と考えられており、フィレンツェ大学のスリコは、これを4つの病害に分類することを提案しました。すなわち、ブラウン・ウッド・ストリーキング、ペトリ病、若い樹に見られる葉の縞模様の病害、そして白腐病と呼ばれるエスカです。葉の縞模様と白腐病が同時に見られる場合は「正規のエスカ」と診断されます。ヨーロッパでは、これらが同時に発生することが一般的です。
この複合病の研究では、どの真菌がどのように関与しているかの解明が目的とされています。関係する菌は、維管束病原菌のPhaemoniellaやPhaeoacremonium属、白腐病を引き起こすFomitiporia属などです。しかし、これらの菌は症状のある樹とない樹のどちらからも検出されることがあり、ストレスや環境変化によって発病する潜伏病原体である可能性が示唆されています。近年はシーケンシング技術を用いて、発症樹と健全樹の微生物構成の比較が進められていますが、品種によって結果は異なり、明確な因果関係はまだ示されていません。細菌が真菌の働きを抑制する可能性も指摘されています。
ロワール地方では特にエスカが問題となっており、古い区画では樹の欠損が目立ちます。ソーヴィニヨン・ブランやシュナン・ブランなど、影響を受けやすい品種も知られています。フランス全土での発症率は約13%と推定されます。かつてエスカは大きな問題ではありませんでしたが、2003年に防除に用いられていたヒ酸ナトリウムが禁止されたことで、発症が顕著になりました。現在は「キュレタージュ」と呼ばれる、幹内部の病変部を除去する方法や、剪定方法の見直しが進められています。
日本では、ワインの栽植が始まって日が浅いため、これまで見過ごされがちだったように思います。しかし、樹齢を重ねるにしたがってこの問題が顕在化する可能性は否めません。フランスで問題とされている地域の一つは、ロワールです。寒冷地での栽培を試みる日本にも似たようなリスクがあるかもしれません。
(写真は、ラグフェイズの101-14の樹齢20年ほどの古木。エスカの症状は見られませんが、台木の生産効率は樹齢とともに下がりつつあり、苗木生産の目的としては植え替えが必要と考えています。)
詳細は、『新ブドウ栽培学』第16章に記載されています。