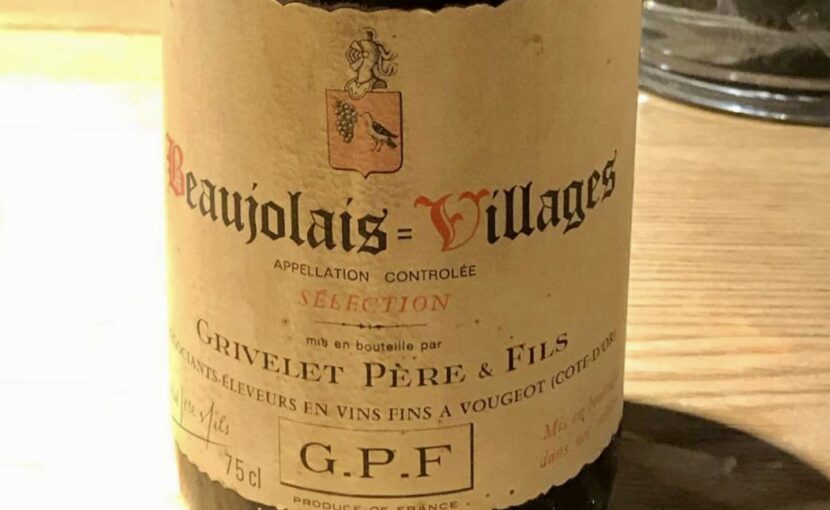1997年、カナダの研究者スザンヌ・シマードの発表した研究は、森林に対する考え方を大きく変えました。彼女は、樹木が単独で生きているのではなく、地下の菌類ネットワークを通じて互いに資源や情報をやり取りしていることを示しました。シラカバとダグラスモミを対象に炭素の放射性同位体を使った実験では、木々が炭素(糖分)を交換していることが確認されました。このネットワークは外生菌根菌(EMF)が媒介しており、異なる樹木の根をつないでいます。
この発見は、森林が「協力し合う共同体」であるという新しい見方を生み出し、「ウッドワイドウェブ(wood wide web)」として知られるようになりました。ドイツの森林官ペーター・ヴォールレーベンの著書『樹木たちの知られざる生活』によって広まり、科学的な裏付けを持ちながらも、親しみやすい形で多くの人に伝わりました。
同様の現象はブドウ畑でも起こりうると考えられています。ブドウ樹も菌根を持ち、他の植物と資源を共有している可能性があります。2004年、カリフォルニア大学デイヴィス校の研究では、ブドウ樹と被覆植物を使った温室実験で、アーバスキュラー菌根菌(AMF)を介して栄養素が移動していることが確認されました。ナパ・ヴァレーの調査でも、ブドウ樹と被覆植物の根が菌根を共有していることが明らかになっています。
古いブドウ畑では、ブドウ樹どうしがこのネットワークでつながり、病気や環境ストレスを互いに知らせ合っている可能性もあります。ただし、こうした仕組みが働くには、土壌生物が健全であることが前提です。耕起はAMFを減少させるため、耕起を控え、被覆植物を利用することで、菌根菌が約30%増加することが報告されています。
詳細は、『新ブドウ栽培学』第4章に記載されています。